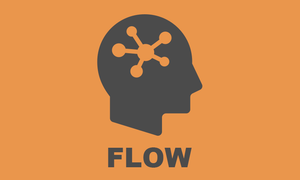書籍「学び方の学び方」を読んで学んだ学び方を紹介します

こんにちは、ぶちやです。
突然ですが、最近何かを勉強したり学んだりしていますか? 私は社会人になってからというもの、日々何かしら学んでいる気がします。 それは受動的な学びから自らの意志で身につけようとする学びまで様々です。 自分なりに学習してきましたが、理解するまでに時間がかかることも少なくありませんでした。
最近、「学び方の学び方」という書籍を読了しました。 学び方を学ぶという今まで意識してこなかった内容でとても興味深かったです。 今まで見聞きしてきたこととで知っていることから新しい発見までいろいろと書かれていてとても参考になりました。
今回は書籍「学び方の学び方」を読んだ上で私なりの学びを効率化させる方法を紹介します。 あくまでも私というフィルターを通した内容となっており、書籍には書かれていないことも多分に含んでおります。 書籍をもとに書いていたら長文になってしまったので、目次を読んで興味のあるところを読んでいただければと思います。
目次
- はじめに
- 環境を整える
- 集中時間と休憩時間でメリハリをつける
- より深く学習する方法を活用する
- 作業記憶を最大限に活用する
- 自分の心をうまくコントロールする
- 読書と試験の向き合い方
- 脳内監督で自分自身を観察してコントロールする
- さいごに
はじめに
書籍「学び方の学び方」は効率的かつ効果的に学ぶ方法が詰まったハウツー本です。 2021年1月30日に発行されました。 著者は以下の2名です。(書籍の著者紹介欄から一部抜粋)
バーバラ・オークレー 工学博士。ミシガン州ロチェスターにあるオークランド大学教授で、2018年度ミシガン州優秀教授賞受賞。コーセラ(2012年にアメリカで創立された教育技術の営利団体)創立以来の”イノベーション・インストラクター”である。
オラフ・シーウェ ノルウェーのオスロにある教育テクノロジーのスタートアップ企業、エデュカスの創業者兼CEO。学生のよりよい学び方のソリューションの開発に取り組んでいる。
書籍「学び方の学び方」は読書に学習のテクニックを伝え、学習の取り組み方を改めることで学習の効率を大きく向上させようとという趣旨で書かれています。 本書の「最後に」の部分で以下の言葉を添えて締めくくられています。
読者が本書から得た最大の知見は何か? 学習を進めていくうえで、今後、今までとはどんな違ったことをするつもりか?
私は読んで学んだことを自分の経験と合わせて理解を深めるためにこの記事を書くことにしました。 この記事を通して何かしらのキッカケになれば幸いです。
それでは学びを得た内容を紹介していきます。
環境を整える
邪魔になりそうなものは排除しておく
学習に集中するためには、集中力を切らさないようにする工夫しておくと捗ります。 以下のような工夫をしておくと良いでしょう。
- スマホの通知を切る、機内モードにする、 電源をオフにする(突発的な呼び出しを遮断する)
- 机の上には学習するものだけにする(誘惑されるものを視界に入れない)
集中時間と休憩時間を設ける
効率よく学習するためには以下の2点が必要不可欠です。
- 学習中は徹底的に集中する
- 脳を休めるために休憩する
後述しますが、休憩が学習にとって必要なことです。 集中時間と休憩時間を分けて効率的に学習しましょう。
集中と休憩をより効果的にするならばポモドーロ・テクニックを活用してみると良いでしょう。 ポモドーロ・テクニックとは、事前に決めた時間配分で集中と休憩を繰り返す手法です。 25分の集中と5分の休憩がスタンダードですが、時間配分は各自でカスタマイズすると良いそうです。 以下の点を踏まえるとあまり長すぎないほうが効果的と言えるでしょう。
- 集中力は長続きしない
- 最初と最後は記憶に残りやすいが中間は記憶に残りにくい
学習中の取り組み方
学習中の具体的なコツは後述しますが、取り組み方は以下を基準に取り組みましょう。
- シングルタスクで一点突破(マルチタスクはスイッチングコストがかかり成果が下がる)
- 他の作業やアイディアが浮かんで気が散ったらそれを外(紙やPC)に書き出す
- BGMは歌がない曲で落ち着いた曲にする(音楽が気になると集中できなくなる。集中できなければ聴く必要はない)
休憩中の過ごし方
休憩中は脳を休めることによって学習の質が上がります。 脳をしっかり休めるように過ごしましょう。
- スマホやPCは使わない
- 本を読まない
- ストレッチやヨガ、軽い運動をする
- 歩く(トイレに行く、飲み物を取りに行く等)
- 目を閉じる
集中時間と休憩時間でメリハリをつける
学習中に集中できていると、その後の休憩時に脳が拡散モードに入る仕組みになっています。 拡散モードの仕組みや効果的な利用方法は以下です。
- 拡散モードの時に脳内が整理される
- 行き詰まって集中力が切れたら自然に拡散モードに入っていく
- あるテーマで集中モードに入りながらも同時に別のテーマが拡散モードに入ることが可能
- 拡散モードに入るには真剣に集中しなければならない
- 拡散モードのタイミングから逆算して集中時間を検討する方法もある
- 難しい問題から着手すると拡散モードを効果的に使える
- 執筆時は集中モードで草案を書ききり拡散モードで推敲する
より深く学習する方法を活用する
学習をより深めるにはいくつかの方法があります。
積極的に学習する
積極的に学習する、というのは積極的に学習内容を思い出したり自分の言葉で要約したりする活動のことです。 具体的には以下のような方法です。
- 問題に取り組み中は答えを見ない(自力で思い出して解答する)
- 自分の疑問をまとめる
- 子どもに説明するかのように要点を簡単な言葉に変えて説明する
- フラッシュカードを作り取り組む
- 日常的な活動中にキーポイントを思い出す
- 動画の視聴後や読書後すぐに要点を見極めるように努める
回収活動を意識しておこなう
回収活動とは、自分の記憶から情報を引き出したい、それを見たい、自分の頭でそれを活用したい、と思いながら思い出す活動のことです。 思い出す行為は、長期記憶から情報を引き出すようになっています。 長期記憶から情報を引き出して回収しようとすると長期記憶に定着していき、結果として思い出しやすくなります。 簡単に回収できる(思い出せる)ものはよく理解している証拠です。逆に回収できない(思い出せない)ものは理解不足なのでもっと学習が必要だとわかります。 理解できているかの指標として回収活動を意識すると良いでしょう。
自己説明もしくは推敲して積極的に学習したことを整理する
上記でも述べた通り、積極的に学習することが重要です。 自分の言葉で説明しようとすると理解がより一層深まります。 以下のようなことを脳内でも構わないので実際にやってみると良いでしょう。
- 学習内容を整理してもう一人の自分に言葉で投げかける
- 推敲して学習内容の理解を深める
ほとんど忘れてしまってから改めて学習するのが理想的な間隔の空け方
まとめて学習するよりも休憩を挟みながらの方が効果的です。 その理由は脳が休んでいる時に脳内で情報が整理されるからです。 そして寝ている間はより脳内の情報が整理されます。 1日に分けて学習するのも良いですが、日にちを空けてほとんど忘れてしまってから改めて学習すると脳内が整理された状態なので効果的に理解できます。
近いテーマを交互に学習する
拡散モードの話で「あるテーマで集中モードに入りながらも同時に別のテーマが拡散モードに入ることが可能」と説明しました。 拡散モードを効果的に利用して学習を加速する方法として、以下の方法を試してみると良いでしょう。 以下は学習教材を本として説明します。
- メインテーマを決める
- メインテーマ、同じテーマで違う本、近いテーマの本のそれぞれの学習教材を用意する
- 上記3つを学習時間25分、休憩時間5分のまとまりで交互に学習する
学習の直前に運動する
様々な研究で学習前に運動をすることにより成果が上がる結果が出たそうです。 週3回20分間高負荷のインターバルトレーニングをおこなうと良いでしょう。 忙しい場合はタバタトレーニングなどの4分間トレーニングでも効果があるようです。
認識機能を強化する飲食
以下は一定の効果があるそうです。
| 栄養 | 飲食物 | 効果 |
|---|---|---|
| カフェイン | コーヒー、紅茶、緑茶、ガラナ | 15分で注意力を高める効果 (飲みすぎると睡眠の妨げになる) |
| 炭水化物 | ドーナツなど砂糖入りのもの | 15分で覚醒作用を起こす効果 (食べすぎると眠くなる) |
| フラボノイド | ココア、緑茶、カレー粉(クルクミン) | 6ヶ月後に学習と記憶を司る分子構造を改善する |
睡眠の質を上げる
睡眠の質を上げることによって脳がリフレッシュされて学習効率が上がります。 寝る前に以下のようなことをできる範囲で取り入れていくと良いでしょう。
- 脳内の考え事を書き出し切る
- 照明の明るさを少し落とし温かい色にする
- 部屋の温度を18度前後に保つ
- ストレッチする
- アイマスクをつけて寝る
作業記憶を最大限に活用する
作業記憶には限界があります。 1度に3〜4件ほどしか一時的に保持できないようになっています。 作業記憶を最大限に活用するために以下のような方法を取り入れてみると良いでしょう。
簡単にする
難しいものは自分なりに整理して理解できるようにします。
- 要点をまとめる
- 対象を分解して簡単に理解できるものを積み重ねる
- 理解しやすい言葉に翻訳する
- なじみのあるものに結びつける
紙やPC、スマホなどにアウトプットする
脳の外にアウトプットすることで作業記憶がそこまで拡張されます。 その際に以下を念頭にアウトプットしていくと良いでしょう。
- 要点を抽出して自分なりに整理する
- 概念図を書く
- 1日が終わる前にノートの内容を思い出す作業をする
- 大切な内容を頭に入れる
- 眺めるだけでは長期記憶には記憶されづらい
記憶して内在化する技
以下のような手法を用いるのも理解が捗ります。
頭字語 頭文字を集めて覚えやすくする手法。 古代ギリシャの三大哲学者の名前を覚えたい場合は以下のような言葉で覚える。
SPA
S: ソクラテス P: プラトン A: アリストテレス
連想する文章をつくる 本書では例として以下のような文章が挙げられていました。
My Very Elderly Mother Just Served Us Noodles. (私の年老いた母が私たちにヌードルを食べさせてくれた)
これは惑星の順番と文章の頭文字の順番が一致した覚え方だそうです。
- My (Mercury 水星)
- Very (Venus 金星)
- Elderly (Earth 地球)
- Mother (Mars 火星)
- Just (Jupiter 木星)
- Served (Saturn 土星)
- Us (Uranus 天王星)
- Noodles (Neptune 海王星)
日本語ではそれぞれの漢字の頭字語として「水金地火木土天海」で覚えている方も多いかもしれません。
自分の心をうまくコントロールする
人の心は誘惑に弱い生き物です。 誘惑に負けない対策をしっかりすることで学習に前向きに取り組めます。
自立心に頼らない方法を組み込む
学習開始のトリガーを決めておく 学習を開始する前に学習を始めるか考える時間が1秒でもあると怠け心が出てきます。 一瞬でも怠け心が出ると学習が苦痛になってしまいます。 逆に学習以外の他のことをやっている時に「これの後はあの学習をしよう」と決めて、他のことが終わり次第に流れるように学習を開始すると心理的負荷が少ないです。 トイレに行った後、食事後、帰宅後、なんでも構いません。 重要なのは、学習前に学習するか考えないことです。
学習の開始のハードルを極限まで低くする
1日の目標を極端に低く設定します。 「これぐらいすぐできるだろう」と笑い飛ばしたくなるぐらいがちょうど良いです。 もしくは体調が悪い時でも達成できるレベルのものにすると考えても良いかもしれません。 そうすることで学習に着手しやすくなります。 例えば以下のようにすると良いでしょう。
- 試験対策: 1問だけ解く or テキストを開くだけ
- 読書: 1行だけ読む or 本を開くだけ
- 英語: 目に止まった英単語1語だけ調べる
もし上記でも着手できない場合はもっとハードルを下げると良いでしょう。 机に向かって椅子に座る、学習するもの(本など)を眺める、など自分の今の状況に応じて設定すると良いでしょう。
邪魔になっている習慣を変える
ついやってしまって気がついたら学習の手が止まっている、そんな習慣がもしあるのならば改める良い機会かもしれません。
- 勉強中についスマホでSNSを開いてしまう
- →スマホの通知を切って手の届かないところに置く
- 音楽を聴きながら勉強していて気づいたら選曲に夢中になっていた
- →好きな曲を聴くのではなく自然音のBGMなどを聴いて音楽が気にならないようにする
目標を立て、誘惑への対策をする
具体的に計画を立てましょう。 いつ、どこで、どのようにして目標を達成するか明確にしましょう。 学習中に友人の遊びの誘いが来たら「他に予定がある」と前もって回答する内容を決めておくと良いです。学習中のあなたに必要なのは遊びではなく、取り組んでいる学習です。
楽しむ時間を確保しておく
学習ばかりだと疲弊して長続きしない可能性があります。 楽しむ時間もしっかりと計画しましょう。 楽しむと決めた時間は好きなように自分の心の赴くままに楽しみましょう。
やることを期限つきで周りに宣言する
周りに宣言することで「守れなかったら恥ずかしい」という気持ちになり、恥ずかしいを原動力にして期限までに終わらせようという気持ちにさせてくれます。
自分自身をその気にさせる
学校や仕事の関係でやらないといけないからなどの外発的動機付けでは長続きするのは大変です。 自分自身をその気にさせることができたなら意欲的に着々と進めることができます。 以下の4つのことを意識して学習の外堀を埋めていくことで、意欲を沸かせて維持することができるでしょう。
- 価値を明確にする
- 達成感を味わう
- ゴールを具体的に設定する
- 協力者を見つけ活用する
価値を明確にする
まず初めに学ぶ内容に対して自分が学ぶ価値を明確にします。 学んだ結果、どうなることを期待しているかを明確にします。
- どういった報酬があるか
- どう活用したいか
- 自分にどんな得があるか
- どう役に立つか
つまり、
「自分がそれを達成して嬉しいことはなんですか?」
ということを明確にします。 これは目的ではなく自分にとっての価値を見極めるために明確にします。 価値が動機になります。 価値が低いとやる気も同じぐらいの弱さになります。 価値を明確にするほどやる気も強くなっていくでしょう。
達成感を味わう
達成した時の喜びは気持ちがいいものです。 またあの時の感動をもう一度味わいたい、達成感はそう思わせてくれます。 ただ黙々とタスクをこなすように取り組むのではなく、達成感を味わいながら取り組んでいきましょう。
- 進捗が後からでもわかるように可視化する
- 積み上げるような指標だと達成感を味わいやすい
- 例)学習時間、理解した用語数 等
- 積み上げるような指標だと達成感を味わいやすい
- 定期的に振り返りをおこない達成感を味わう時間をつくる
- 理解が進まない時は簡単に理解できるレベルからやり直す
過去に取り組んだ事実は消えません。 取り組んだ時間、学んだ用語や概念など記録できるものは記録しましょう。 1万時間の法則というものがあります。 取り組んだ分だけ前進しています。達成感を味わいましょう。
ゴールを具体的に設定する
自分が向かうべき場所、向かっている姿を明確にして学習に気持ちを乗せましょう。 以下の3つのゴールを設定して目的地や手段を明確にしましょう。
| ゴールの種類 | 内容 |
|---|---|
| 最終ゴール | ・自分をわくわくさせてくれるもの ・思い浮かべる度に良い気持ちにさせてくれるもの ・最終ゴールを想起するような写真や物理的なものを手近に置いておく |
| 中間ゴール | ・最終ゴールに繋がるものを設定する ・半年から3年後くらいにどうなっていたいかで設定する ・現在から最終ゴールまでの間に何層重なっても複数あっても良い |
| プロセスゴール | ・具体的な行動のゴールを設定する ・日単位もしくは週単位等の短い期間として設定する ・学習時間ややったかどうかなどで設定すると良い |
上記3つのゴールを適切に設定することが重要です。 適切なゴールはSMARTのフレームワークを活用することでより良くなります。
SMART
| Specific | 具体的 |
| Measurable | 測定可能 |
| Achievable | 達成可能 |
| Relevant | 関連性のある |
| Time-bound | 期限のある |
協力者を見つけ活用する
学習は孤独に向き合うばかりではありません。 周りの人やコミュニティなどをうまく活用して自分に活力を与えてくれるものを見つけましょう。
- 一緒に取り組める人を探して一緒に取り組む
- 同じコミュニティ内で話題にして盛り上がれる人を見つける
- コミュニティ内で意欲満々で前向きな姿勢を見たらやる気が上がるかもしれない
読書と試験の向き合い方
読書の効率的なインプット方法
読書で効率よく学ぶには以下を意識します。
- 理解力を上げる
- 解像度を上げていく
- 注釈を入れる
理解力を上げる
まず前提の話ですが、本を読む速度は理解力によって変わってきます。 理解力を上げるには以下が必要になってきます。
- 豊富な語彙
- 教養
- 豊かな読書経験
本の文章を書いた人はその人が今まで得てきた知識や言葉を使って文章にしています。 豊富な語彙があることで本のテーマを理解するのが早くなります。 知らない言葉があると理解がぼんやりとしてしまいます。 理解するために知らない言葉を辞書で調べたりしないといけなくなりますが、知らない言葉が多いほど本のテーマを学ぶことから離れてしまいます。 専門書を学ぶ時は特に専門用語や難しい概念が多いかもしれません。 知らない言葉が多いと読む速度が遅くなりますが、それを承知の上で少しずつ読むのは良いと思います。 しかし、あまりに進む速度が遅いのが気になるようであれば、理解しやすい本にレベルを落とすことで途中まで読んでいた専門書の理解が進むかもしれません。
教養とは、どのような専門性にも 通用する幅広い基礎的な知識のことです。 学校で学んできた国語、数学、理科、社会、英語のようなものを思い浮かべるとわかりやすいかもしれません。 本の中で難しい言葉を使っていたり違う国の都市のことが書いてあったり普段使わない英単語が出てくるかもしれません。 教養はここまで知っていたら良いというものではないので、その都度学んでいくしかありません。一つずつ身につけていきましょう。
豊かな読書経験があると本を読む速度が上がってきます。 本を早く読みたいのに読書経験がたくさんないと早く読めないというのは残念に思うかもしれません。 なぜ豊かな読書経験が必要か説明していきます。 まず、文章には書く人の癖が少なからず出ます。 書く人によって読みやすかったり逆に読みにくかったりする場合があります。 これは本のテーマの難しさとはまた別の要因だったりします。 書く人が好んで使う言葉や表現が存在します。 本は著者との対話と考えるとイメージしやすいかもしれません。 文章が丁寧だったり煽っていたり、固い表現だったり優しく伝わりやすい表現だったりと著者が自分に話していると考えるみると、人には口癖があるように書く癖もあるということがイメージできるのではないでしょうか。 そのような癖はいろんな本を読んでいろんな癖に慣れる必要があります。 本を読んで理解するということは、本の文章を書いた人の知識を理解したり経験してきたことを想像したりすることです。
読書の効率を上げる方法を2つ紹介します。
解像度を上げていく
本を最初から順番に読んで最後まで読もうとする方は多いかもしれません。 本を最初から最後まで読んだ後、その本には何が書かれていたか説明できるでしょうか。 おそらくなんとなくでしか説明できないのではないかと思います。 小説や漫画等は物語なので最初から読んで楽しむのが良いでしょう。 しかし、ビジネス書や専門書等は自分が知らない知識を得るために読むものではないでしょうか。 ここでは本のことを主にビジネス書や専門書等のこととして進めていきます。 本から知識を得る場合、本の読み方にはコツがあります。 それは、解像度を上げていくように読むことです。 解像度とは、どれぐらい鮮明かを表現する言葉という意味でざっくりとイメージしてください。
例えば散歩している時に地面に蟻を見つけたとします。 立った状態で見た蟻は黒い塊ぐらいにしか見えないかと思います。この状態は解像度が低いと表現します。 逆に座って蟻にぐっと近づいた状態で蟻を見ると、足が一本ずつはっきりと見えたり触覚も見えたりと立った状態よりも具体的に見えるかと思いますこの状態は解像度が高いと表現します。 このように見る視点によって解像度が違います。 本を読む前は立った状態でも読み終えた時には座った時のように解像度が高い状態が望ましいといえるでしょう。
本の内容の解像度を上げていく、理解度を上げていくには大枠から理解していくと本の内容がスムーズに入ってきやすいです。 ここで本とはどのようなものか、視点を変えて説明します。 本は著者が主張したいことについて体系的にまとめた媒体です。 誰が何をいつ書いたか、という視点があると理解が深まります。
タイトル どのようなことが書かれていそうか、何について知ることができるだろうか。 学びたいことを学べそうかで判断して手に取ってみると良いかと思います。
著者プロフィール どのような人がどのような立ち位置で書かれているかが判断できます。 教授などの権威のある方なのか、その道のスペシャリストなのかプロフィールを読み解いて判断します。 しかし、権威がないからといって得られるものがないわけではなく、逆に権威があるからといって内容が良いかは読んでみないとわかりません。 ポジショントークのような内容が入る可能性もあります。 書いてある内容が信用できるかどうかは似たテーマで異なる著者の本を数冊読んで判断するのが良いでしょう。
本の発行時期 本の発行時期はとても重要です。 書いてある内容に対して古いか新しいを判断する基準となります。
情報がアップデートされていくような内容の場合、古いと役に立たない可能性があるのでなるべく新しいものを選ぶようにしたほうが良いかもしれません。 例えば、IT系の技術書などで言語やツールの本であれば使いたい言語やツールのバージョンと合っているかよく検討した方が良いでしょう。
逆に古くから変わらない内容のものは古くても多くの方から支持されている有名なものを選ぶと良いでしょう。 ビジネス書だと七つの習慣や金持ち父さん貧乏父さんなどが挙げられます。
本の内容の解像度を上げていく方法として大枠から理解していくと説明しました。 読む順番を説明していきます。
- 目次
- まえがき or あとがき
- 章の見出し、太字、図版、まとめ
目次 まず、目次で本の全体像を把握します。 目次を読みながら興味を惹かれる章があればそこから読むために把握しておきます。 どうしても気になる場合はサッとその部分だけ読んでみても良いかと思います。 目次を一通り読んで自分が読むに値するか検討します。 興味を惹かれる章の見出しがたくさんあって読みたいと感じるのであれば読むと良いでしょう。 少しだけ気になるようであればそこだけ読むと良いでしょう。 ちょっと違ったなと感じたらその本は合っていないか、まだ読むタイミングではなかったのかもしれません。
目次はその本を読むか判断するのに最適です。 あまり目次を読む習慣がなかった方はぜひ読むようにすることをおすすめします。
まえがき or あとがき 著者が本を書く前、もしくは書き切った後に書く部分なので著者が力を込めている部分となります。 その本を書いた動機や経緯、本の概要などが書かれていることが多く、本とどのように向き合ったら良いか判断しやすいです。 専門書であれば初学者向け、中級者向け等のことを書いてくれている場合もあるので自分がその本の対象者であるか判断することができます。 目次で興味を持ったらまえがきやあとがきも読むようにしましょう。
章の見出し、太字、図版、まとめ 目次やまえがき、あとがきで本がどのようなものかざっくり把握できるかと思います。 ここからは基本的に気になった章から読み進めていくことをおすすめします。 人は興味のあることは吸収しやすい性質を持っています。 章の最初から順番に読み進めていくのも良いですが、章の見出し、太字、図版、まとめを最初にざっと見て把握しておくと理解が早いかと思います。 興味のあるところを読んだ後は、他の章も見出し、太字、図版、まとめを中心に拾って読んでいくと目次から一歩進んだ概要が把握できるようになってきます。
ここまでは本屋で立ち読みしていてもできることかと思います。 その本を本当に時間をかけて読むべきか判断する作業になります。
次からは実際に本を手に入れて本を読みながら作業をおこないます。
注釈を入れる
本を片手にやることは2つです。
- 本に目印をつける
- 紙やPCにまとめる
本に目印をつける
実際には電子書籍だったり図書館で借りてきた本の場合もあるでしょう。 電子書籍であればマーカー機能等を使い、返す予定の本は付箋やポストイットを使って本を汚さない方法を取ると良いでしょう。 大事なことはざっと読み進めている時に後で必要な言葉を拾い集められるようにすることです。
- 後で調べるキーワードや概念
- 金銭に触れた名言
- 重要なアイディア
- 理解できない情報、明確化が必要な情報
紙やPCにまとめる
主要な段落ごとに自分なりの要約をアウトプットしましょう。 なるべく自分の言葉に置き換えた表現でまとめるようにすると理解が深まります。 その際、自分自身の例や参考になるものを結びつけるとより自分ごとになります。 概念図などの図示や絵にすると視覚としても覚えやすくなります。
試験で好成績を上げる方法
試験に合格するための効率的な学習方法があります。 なぜその学習方法が適しているのかを理解して取り組むと良いでしょう。
- 過去問をできるだけ数多くあたる
- 試験当日までの勉強計画を立てる
- 当日の時間配分を常に考える
- 難しい問題から着手する
過去問をできるだけ数多くあたる
試験勉強は試験に合格するためと割り切って取り組みましょう。 教科書を読んでしっかりと理解したい、という気持ちはわかります。 もちろん教科書を読んで理解することは大切なことです。 しかし、試験でどういった設問でどういう解答なのかをしっかりと把握していないと正解するのに時間がかかったり間違った解答をしてしまうかもしれません。 試験合格に必要なのは基本的な理解と試験対策です。 多くの試験では過去に出した問題を出したり、ちょっと変えた表現で出したりします。 それに過去問を多く解いていくうちに傾向が見えてきたり何が重要とされているのかが見えてくることがあります。 教科書で知識をインプットすることも重要ですが、それと同じ以上に過去問にしっかり取り組むことが重要です。
試験当日までの勉強計画を立てる
試験日は決まっています。 試験によっては年に数回しか開催されないものもあるでしょう。 試験日に照準を合わせ当日までの勉強計画を立てましょう。 試験範囲の中からどの科目にどれぐらいの時間を割くか時間配分を決めましょう。 試験で配当が高いものほど重要なので時間を多めにしても良いでしょう。 試験までにしっかり理解して解けるようにしようと思っても大抵時間が足りない、ということはよくあることです。 ある程度割り切って勉強計画を立てたらその計画通りに進めていきましょう。
当日の時間配分を常に考える
試験当日、試験開始から終了時間までにどこをどれくらい時間が使えるか把握することで冷静さを保つことができます。 想定より時間がかかっている場合、そこを捨てて他で点を取りにいくという選択もできるようになります。 一番もったいないのは、時間配分を気にせず順番に解いていって途中で詰まり、時間がなくなり後半まったく手付かずになってしまうことです。 時間配分を検討する上で、過去問を試験と同じ持ち時間で取り組んで計測すると把握しやすくなります。
難しい問題から着手する
拡散モードをうまく使っていきましょう。 難しい問題から着手し、行き詰まったらある程度で見切りをつけて他の問題に取り掛かります。 そうすることで他の問題を解答中に無意識下で難しい問題について拡散モードに入ります。 無意識下で閃くのを期待しましょう。
脳内監督で自分自身を観察してコントロールする
あらゆるタイミングで脳内監督を自分自身の中にイメージすることをおすすめします。 自分自身を脳内のもう一人の自分が俯瞰して監督している、そんなイメージです。 例えば、自分がイラっとした時、脳内監督として「自分は何にイラっとしたんだろう?」と考えます。 この時、どのように反応するのが適切なのかを考えて脳内監督として自分に指示します。 こうすることによって感情的にならず適切に判断して行動することができるようになります。 このような脳内監督のことをメタ認知と言います。 学習面においてもこのメタ認知は有効活用できます。 メタ認知が働く質問を自分自身に問いかけるようにしましょう。
- 学習時、集中している対象は適切か(気が散っていないか)
- 学習教材のレベルは適切か(理解できているか、レベルを下げるか)
- 計画通りに進んでいるか(計画の見直しは必要か)
- ゴールは適切か(わくわくするか、具体的か)
さいごに
効率的に学ぶ方法をたくさん紹介しました。 合うもの・合わないもの、共感する部分や違った見方をしている部分などあったかと思います。 他者の考えを知り自分に落とし込んでいく作業はまさに学びです。 学びを得ることは喜びを感じることもできます。 学びを前向きに捉え、新たな知見を得ることでより良い人生にしていきましょう。 私からは以上です。
お読みいただき、ありがとうございました。